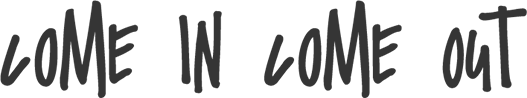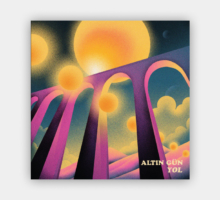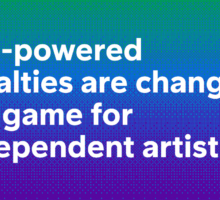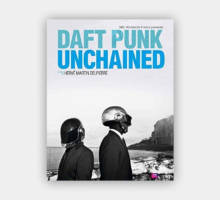ごきげんよう。音楽関連の記事やエントリーを紹介(記事みて記事書く簡単なお仕事です)、と思ったのですが、夏フェスにおける「ハレとケ」が結構長くなってしまいましたので独立させました。
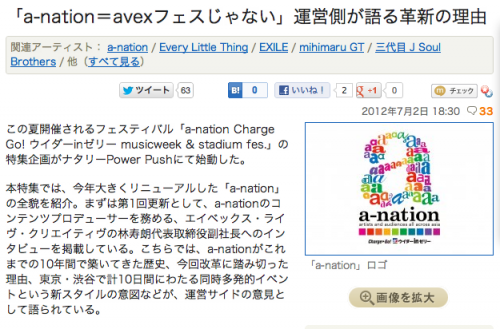
「a-nation=avexフェスじゃない」運営側が語る革新の理由
11年目を迎える、エイベックス主催の恒例フェスティバル「a-nation」が、開催11年目の今年、大胆なリニューアルを遂げる。2012年8月3日/4日/5日/9日/10日/11日/12日に国立代々木競技場第一体育館・SHIBUYA-AX・渋谷WWWを使用して日毎に異なるジャンルでライブイベントを実施する「musicweek」。さらに、8月18日/19日に大阪府 長居陸上競技場(長居スタジアム)、8月25日/26日に東京 味の素スタジアムを使用した「stadium fes.」を開催。
ナタリーの特集ではイベントのプロデューサーや出演アーティストへのインタビューで、このフェスの魅力を紐解いていく、とのこと。
この「a-nation」、そもそものコンセプトは「音楽のテーマパークを作りたい」というもの。
単なるフェスではなく、音楽を中心としながらいろんなエンタテインメントの楽しみ方を提案していこう
と特集の中で書いてありますが、このような音楽だけではなく、それ+αでエンターテイメントをパッケージ化して売り出すのがフェスの特色ですよね。それがだんだんと完成されていくと、ピークアウトを迎えるしかなくなる。
「つまらない」と言われる原因を考えたときに、やっぱりもうテーマパークじゃなくなってきたのかもなって思ったんです。回を重ねていく中で内容も固定化してきましたし、それによって当然フェスとして定着はしてきているんだけど、一方ではヘッドライナーによってファンが変わってしまう、いわゆる人気アーティストの積み上げ型のフェスになってしまっている。それではほかのフェスとの差別化もできなくなっているんじゃないかと。そこで改めて「イベントそのものをテーマパークとして楽しめるものにしよう」と思ったんです。
「ヘッドライナーによってファンが変わってしまう、いわゆる人気アーティストの積み上げ型のフェス」と聞いて真っ先に思い浮かべたのがSummer Sonic。Fuji Rock Festivalがひとつのテーマパークとして、出演アーティストに左右されずに参加する、いわゆるフジロッカーというロイヤルカスタマーを獲得しているのに対して、Summer Sonicへの参加はアーティスト次第なところがある。あくまでも、これは僕の肌感ですが。
なぜそのように感じるのか。僕は、Fuji Rock Festivalは完全な「ハレ」であり、全く「ケ」の部分を見せないからだと思う。もともとハレとは、折り目や節目を指す概念であった。語源はそのまま「晴れ」だ。「晴れの舞台」「晴れ着」といった言い回しで使用される。ケ(褻)はふだんの生活である「日常」を表す。
Fuji Rock Festivalは1年に3日間のハレ期間を作り上げる。観光地・観光イベントとして、湯沢全体で盛り上げようとしていることや、苗場スキー場という場所(自然の中)もあって、全く「ケ」を意識させない。それに自然の中というマゾ要素があるから、感動も大きい。もともと祭ってマゾ要素のあるものですよね。汗水たらして神輿担ぐとかさ。という感じで、Fuji Rock Festivalは閉鎖的で、完全な祭として機能している。「ハレ」の中で「ケ」での「ケガレ」を落とすことに集中できる。
対してSummer Sonicはどうも「ケ」がちらつくんですわ。現実感があって、非現実性が希薄。大きな一因として立地があるでしょう(ちなみにこれ、東京会場の話です)。そして、地域全体で盛り上げようとしている感のなさ。ロッテリアくらいでしょうか。他にも盛り上げようとしているところはあるのかもしれませんが、知らないので、ないようなもんです。だからSummer Sonicが好きとか、毎年行くとかではなく、あのアーティストが見たいから行く。Summer Sonicはジャンル問わず、割と旬なアーティストを呼んできますよね。チャングンソクとか?わかんないけど。
大都会だし、電車走っているし、意外と11時くらいで店閉まるし、周り何もないし。地域全体を活用して「ハレ」を作り上げないと、その地域に来ていることを意識させないと、マナーも悪くなると思うんです。中途半端に「ケ」が見え隠れするから、遊びに本気になれない。だって何これ↓

今回の「a-nation」は渋谷という街全体を使って音楽シーンを表現する(そもそも渋谷という街が「ハレとケ」で言うとどっちなのかっていうと、まぁ人それぞれですわな)。「a-nation」は渋谷の街にあるカフェや商業施設を巻き込んでいろんなコンテンツを仕掛けて、「ハレ」の空間を作り上げるわけです。渋谷の人たちを「ハレ」の空間に引きこむわけです。渋谷全体を「ハレ」の空間にして、渋谷全体でフェスをやっている非現実感で虜にする。
じゃあそもそもライブって「ハレとケ」どっちなのか?という話。個人差ありますよね。フェスティバルは完全に「ハレ」としてフェス体験をパッケージ化して売りだすことで、顧客を惹きつける。じゃあ普通のライブはっていうと、これは「ケ」の中のささいな「ハレ」くらいの感覚がベストだと思うでんす。クラブ行くとか、バー行くとか、ボーリングするとか。娯楽のレベル的にはそのくらい。この間nothing ever lastsのネルさんとこういう話をしたんですけど。
参考:“楽曲は無料、ライブも無料”の時代を–日本の音楽業界に挑む米国人シンガー
値段と、どのくらいそのアーティストが好きかで「ハレ」具合が変わる中々面白いものだと思います。たださ、もうちょっと「ケ」寄りの「ハレ」になれば良いなって思う。何が問題かって値段ですわな。なんであんなに高いんだ。そもそもコンテンツを作っているアーティストがライブハウスに金支払って赤字ってどういうことやねん。例えば、Bandcampみたいにライブの値段をお客さんに決めさせようぜ。
とかなんとか、そうなってくるとコンテンツビジネスそのもののあり方まで続いていくのでこの辺で。
結論:フェスティバルは「ケ」を介入させない「ハレ」でロイヤルカスタマーを獲得できる。通常のライブイベントはもっと「ケ」寄りで気軽なものにすべし。
なんか当たり前なこと書いて終わった。。。
これ↓すごい。
FOLLOW