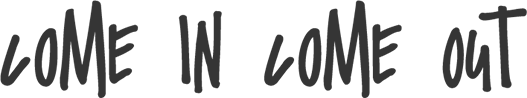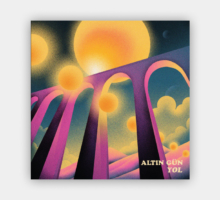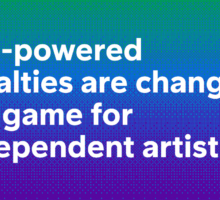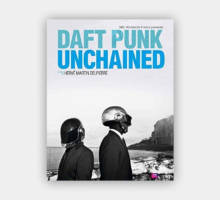Brooklynの23歳、Lorely RodriguezのソロプロジェクトEmpress Ofがニューシングル“Realize You”を公開。BGMにどうぞ。
11月16日に開催されるTOKYO BOOT UP! 2013 Conference Dayで音楽メディアをテーマにしたパネルディスカッションを行います。「音楽メディアはなんでもいい 音楽を広げていく為にできること」というタイトル。誰でも何でもメディアになる今、もっと音楽を広めていくために、もっと深く音楽を語るために何が必要なのか、音楽ファンに何ができるのかを適当にしゃべります。
登壇者は僕(モデレータ)とWEB系編集者のスズキエミリさん、とTwitterでたびたび着火ファイヤーされているFestival LifeのAi_Tkgkさんの3人。職業ライターでも音楽業界でもない3人が外から自由に語ります。なんかもうシュールですよ、きっと。
この日は全部で14のパネルがあり、個人的にもっとも注目しているのはカズワタベさんと小倉秀夫弁護士による「JASRAC独禁法違反訴訟の東京高裁判決が意味するもの」と佐藤タイジさんと永田純さんの「ソーラーエネルギーでライブをやろう! 〜 THE SOLAR BUDOKAN の未来〜」ですね。
他にも音楽プロデューサーの山口哲一さん、ユニバーサルの鈴木貴歩さん、ブロガーのジェイ・コウガミさんによる「音楽サービスの近未来 〜ミュージック・ディスカバリーって何?〜」やフェスをやるほどの音楽好きティーンズによる「ティーンズたちのロックフェス ~ティーンズたちは立ち上がった!なにを感じなにを目指すのか~」なんかも面白そうです。
ちなみにTokyo Boot UP!というは日本版SXSWをやろうという趣旨(だいたい)のイベントでして、過去を振り返ってみるとhemlockとかThe宇宙人ズとかOKAMOTO’Sとかパスピエとか出てて今になっておぉ〜って思います。今年は11月8日〜10日がライブ、16日がカンファレンスとなっています。
≫日本初の音楽見本市<TOKYO BOOT UP!2013>、お互いを高め合う親交の場に | BARKS
≫TBU! 2013メインイベント“MusicDay”、好評のうちに閉幕 | MUSICMAN-NET
で、僕らのパネルなんですけど、先に内容を述べると「音楽が好きな人はいろんなところで、いろんなフォーマットでどんどん音楽を発信しよう。音楽を語ることをもっと日常にしていこう。商業メディアは何のために何をするのか、どうしたら触れてもらえるか、どうしたら音楽との関与度を高められるのか考えろや。」といった感じになるのだと思います。結論は「どんどん音楽の話しよう」です。きっと。
“音楽を語ることを日常”にというのは、「あそこのご飯は美味しい」とか「ちょっとスタバ行こう」とか「先輩がイケメンだ」とか「今日電車でキモいおっさんがいたとか」というレベル感です。例えば女子校生が「今朝フィーチャー・ファンク聴きながら来たんだけどさ〜」みたいな。カフェ巡りか音楽ブログ巡りか、みたいな。放課後や仕事終わりにライブは定番、みたいな。そんな日常になったら超楽しいじゃんと思うんです。
でこれって音楽そんなに好きじゃない人(音楽好きをどう定義するかによる)からしてみると超ウザい。お前のランチなんかどうでもええわ、みたいな。でももうウザくて良いのかなって思うんです。好きなことをもっと語りたいし、好きなものに共感してもらいたい。まずはムラでも良いから好きを語れる場を増やしていったら良い。
日本レコード協会の2012年度「音楽メディアユーザー実態調査」報告書によると、無料聴取層(音楽にお金を支払っていないが、新たに知った楽曲も聞いている)、無関心層(既知楽曲のみ)、無関心層(音楽にお金を支払っておらず、特に自分で音楽を聴こうとしていない)という人が年々少しずつですが増えています。純粋に悲しいし、寂しいですね。
このような現状になった原因のひとつとして、商業音楽メディアが時代に合わせてアップデートを行ってこなかったというのがあるのではないでしょうか。保存性がどうとか、手触りがどうとか、紙VSウェブとか。空想のリスナー像というか(もちろんそういう人もいる)、時代錯誤というか。なんでそもそも読んでもらえることを前提にしてるんだろうって思ってしまう。音楽にお金使ってくれないのに、誰が音楽について語る文章にお金を払うのだろうか。今音楽が好きな人だけでいいのか(しかも減っていってるっぽい)。音楽好きを増やさなくていいのか。
音楽の”情報”にお金を払う人は、本当にマイノリティだと思う。音楽ジャーナリズムは基本的にその対象を掘り下げる行為だと思うけど、それを読みたいという人はどれくらいいるのかな。知らないアーティストだけどレビュー読むって凄いことだと思う。普通は聴取やライブなどの体験がまずあることで、情報に興味を持つ。自分の場合、音楽雑誌は好きなアーティストのインタビューがあるときしか読んでいない。これを想像力がなくなったという人もいるのかもしれません。
じゃあなんで音楽ブログやTiny Mix TapesやPitchforkは見ちゃうんだろうか。なんでこんなに音楽ブログシーンが面白いんだろうか。そもそも自分から音楽を掘っていく人ってどれくらいいるんだろう?音楽ブログを見てる人はどれくらいいるんだろう?それはムラ化していないだろうか?どうやったらムラ同士を繋げられるのだろうか?
(ムラ化しているとしたら)ムラとムラを繋げていく作業が音楽そのものの立ち位置を上げていくことに役立つのではないだろうかと思います。そもそもメディアはそういったものなのですが、特に商業メディアが担ってきた部分なのかもしれません。この辺は具体的に触れたいところですね。targeted serendipityとか。
そのザッカーマンが『Rewire』において指摘するのは、インターネットによりかつては考えられないほど世界中のニュースや知見に触れることが可能になり、実際グローバル化する世界において正しい判断を行うにはそれが必要なはずなのに、現実には外国より国内のニュース記事を優先し、ソーシャルネットワークにおいて自分に近い属性の人間とだけ接し、「フィルターバブル」に安住するインターネットユーザの姿です。
この内向き志向はインターネットだけでなく、実はテレビなど既存メディアにも当てはまることですが、現在のインターネットでは欲しいものは手に入るが、それが本当に必要なものとは限らず、ソーシャルネットワーク隆盛の「つながりの時代」において、本当に必要な情報が見えにくくなっているとザッカーマンは主張します。問題なのは情報へのアクセスではなく、むしろその情報に注意を向けさせること自体なのだと。
世界はまだフラットではなく、グローバリゼーションは始まったばかりで、我々にはインターネットをよりよいものにし、「つなぎ直し(Rewire)」を行う必要があると彼は説きます。
出典:「閉じこもるインターネット」に対するセレンディピティの有効性
“本当に必要な情報”というのがなんのか分かりませんが、情報というのは出会ってみないと必要かどうかわからないので、出会える場所とシクミ・シカケが必要です。
批評とはなにかとか話してたら一生終わらないのでそこは避けようと思っています。そもそもジャーナリズムが何かようわからんし、NY Timesが分からんものは僕らにも分からんし、どうでも良いので誰に向けてどこで何をやっていこう、といった話ができればなぁと。
ただ音楽業界の方が多そうなので、本職を活かしてスマホ対応しないと死ぬよとか、“音楽だけ”商業メディアは死ぬかもよとか、“音楽だけ”職業ライターも死ぬかもよとか、商業メディアやるなら少人数でリッチなコンテンツのほうが良いかもよとか、デザイナーとエンジニア雇えとか、こういうビジネスモデルもあるよ、とか…煽りつつロジカルに触れていければと思ってます。誰が音楽を殺した的な話には何の生産性もないので向かいたい未来の話をしましょうよ(そんなことはどうでいいからやれることとやりたいことをやれよっていう投げやりな結論になる恐れも…)。当日は何卒よろしくお願いいたします。どうせまとまらないと思うのでこのブログでも引き続き発信していこうと思います。
今年(一部昨年)の音楽メディア関連記事をタイムラインにしたものを以下に。資料として当日使うと思います。何かに役立てば幸いです。
2012.09.11
≫過去と未来 田中宗一郎 | THE FUTURE TIMES

2012.11.15
≫「ほぼ日」は売れ筋を”考えない” | 東洋経済
2012.11.16
≫「ほぼ日」はブータンを目指す | 東洋経済
2012.12.23
≫サンデージャーナリズム | 第1回 鹿野淳 ゲスト:金田謙太郎、田中宗一郎、山本博之 | THE PUBLIC
2012.12.26
≫紙の新聞は終わる?――米国では大リストラ | 東洋経済
2013.1.09
≫なぜ新聞は「紙」でないと儲からないのか? | 東洋経済
2013.2.13
≫僕が音楽雑誌を読まなくなった理由 | pitti blog
2013.2.16
≫「音楽メディアユーザー実態調査」から見る今時のリスナー像 -「音楽」と「お金」の不安定な関係 | レジーのブログ
2013.2.21
≫信頼できるのは音楽雑誌ではなく、音楽好きの個人 | pitti blog
1999年と比べて音楽の情報・批評を得る経路は激増しました。僕のような無名のブロガーやtwitterの呟き、amazonの匿名レビューの影響力が少しずつだけど大きくなりました。もちろん依然として音楽雑誌は力を持っているし、雑誌でしか出来ない批評、記事もあると思います。ですが「好き/嫌い」「おもしろい/つまらない」に関して世界一辛辣な感想が掲載されてしまうのがネットの世界であり、twitterやamazonの感想&レビューです。そんな時代に雑誌の制約を受けた賞賛レビューだけが判断材料になるの?と思うのです。
僕が音楽雑誌を読まなくなったのは、ネットの充実も一つの理由ですが、プロ、アマ問わず信頼できる個人の音楽好きを見つけられたことが大きいです。僕はロッキング・オンを信頼するのではなく渋谷陽一を信頼しているのであり、雑誌MUSICAが好きなのではなく特定の書き手の方たちを信頼しているのです。そもそも僕が創刊してから50号まで買い続けたのは鹿野淳さんの批評が読みたかったからです。
2013.2.25
≫音楽雑誌の話題と、知人からオススメについて雑感を | Tempting Soda Records
2013.4.01
≫ホリエモンの考える「新しいニュース批評の形」を勝手に考えてみる |
私もここが最も重要なポイントだと考えています。つまり、どの「社会的出来事」を「選択」し、どのように「取材」するのか。これこそがネット登場以後に最も重要視しなければならないプロセスだと思います。調査報道の種類によっては取材源を秘匿する必要が出てくる場合もあるため、すべてのニュース素材をアクセス可能にすることは難しい。ゆえに誰もがニュースを発信することは事実上不可能でしょう。調査報道を実現するニュースメディアはやはり必要です。
2013.4.08
≫「WHAT’s IN?」「PATi・PATi」が休刊へ | ナタリー
2013.4.06
≫『OTONARI』と柴那典さんインタビューから考える「音楽」と「仕事」の話 | レジーのブログ
— 今回の記事で取り上げている『OTONARI』に関わっている方々もそうだと思いますが、「音楽を発信する側に回りたい/音楽ライターになりたい」という若い人は今でもそれなりのボリュームで存在するのではと思います。最後に、そのような人たちに対して「今の時代に音楽ライターになること」についてのメッセージをいただければと思います。
僕も何回か「音楽ライターになるにはどうすればいいんでしょうか」という質問を受けたことがあります。そういうときは、たいてい「名刺を作ってtwitterのプロフィール欄に“音楽ライター”と書けばなれる」って答えることにしてます。無責任に思われるかもしれないですが、本当にそういう時代だと思います。もちろん、それで食っていけるかどうかは別問題です。
あと、これは質問の回答からズレるかもしれないですが、僕自身や僕の周囲を見回しても「音楽ライター」という職種が、くっきりとそれだけ独立して成立しているような感じはなくなってきているように思います。編集者、ウェブディレクター、プロモーションプランナー、イベンター、USTREAMやニコ生のトーク司会などなど、「音楽について書くこと」以外の仕事を当たり前にこなしている人が多い実感があります。ざっくりとわけると、「メディア(枠組み)を作ること」、「コンテンツ(中身)を作ること」、「評判を作ること」に仕事領域が広がっていて、そこでいろんなタイプの人がそれぞれの得意分野で働いているというか。『ワーク・シフト』で言うところの“連続スペシャリスト”が増えてきているのではないか、と思います。
2013.4.09
≫ワッツインとパチパチの休刊、とても残念です。… | 鹿野淳 Facebook
僕は、紙メディアは音楽ジャーナリストの住処だと思っているし、音楽ジャーナリストである人や、そうなりたい気持ちを持っている人以外が携わってはいけない世界だとずっと思っています。逆に言えば、紙メディア以外に、その機能を果たすメディアは何一つ無いと思っているんです。
これが自分が紙メディアに従事し続け、今やその経営を行っている最大のモチベーションです。だから、音楽雑誌はまだまだ必要なメディアだと思って毎月刊行していますし、これが必要とされないならば、音楽ジャーナリズム自体が必要とされないんだと結論付けようと個人的には思っています。その判断は嫌なので、音楽雑誌は真っ当な音楽ジャーナリズムがそこにあることを、全身で伝えて行かねばならないし、そのレベルを落としてはいけないと、改めて思います。
ワッツインやパチパチの休刊で、紙の役目が云々だの、これらの雑誌の役割がネットになるだの、いろいろ言われるだろうし、実際に既に言われているし、ワッツインに関してはWEBにその姿を変えると、版元さん自身が話されています。
ただ、僕は紙メディアの役割を他の機能を持ったメディアが果たすことは、今の段階では出来ないんじゃないか? 完全に別機関なんじゃないかと思っています。けして古くさい考え方ではなく、それが現実論だと思うんです。そうでなければ、紙雑誌は既に、何年か前に読者を失っていると思うんですよね。
言うまでもなくWEBメディアを認めていないわけではなく、それとこれとは「違う」ということが言いたいのです。逆にWEBメディアの素晴らしさで、自分のフィールドでは一生手が届かないものがたくさんあるとも思っています。
2013.4.22
音楽メディアってなんだ!? – 鹿野淳×大山卓也トークセッション | THE PUBLIC
≫音楽メディアってなんだ!? – 鹿野淳×大山卓也トークセッションのまとめ | togetter
2013.4.26
≫「音楽メディア」を巡るあれこれと、新しい音楽との出会い方 | 日々の音色とことば
テレビもラジオも雑誌もウェブも、ブログもツイッターもYouTubeもニコニコ動画もスマートフォンのアプリも、「それを通して誰かがお気に入りの音楽を知ったり、音楽の楽しさや面白さを知ったりしたもの」は、すべて音楽メディアとして機能していると、僕は考える。もちろん媒体の特性はそれぞれ違うし、伝播力も影響力も違うけれど、あくまで土俵はフラット。全ては人次第。
そして、それぞれの音楽メディアにおいての「影響力」や「信頼」は、決して特別な一部の人、“公人”にだけ備わっているものではない、と僕は思う。誰もがメディアになり、誰もが批評行為を行うことができる。伽藍からバザールへ。そういう風に情報環境が変わりつつある。たとえば「食べログ」や「NAVERまとめ」のアーキテクチャを考えれば、そのことは明らかだと思う。
2013.4.27
≫AOLが自社音楽メディアを全て終了。「Spinner」、「AOL Music」等は消滅 | All Digital Music
2013.4.30
≫20年以上続いた音楽雑誌Vibeが買収される、オンラインメディアとして継続も紙雑誌は廃刊の可能性 | All Digital Music
アメリカの老舗ヒップホップ雑誌「Vibe」が、メディア会社SpinMediaによって買収されることが発表されました。Vibeは1992年にクインシー・ジョーンズとタイムワーナーによって刊行され、ヒップホップ業界でも長きに渡り影響力の高いメディアへと成長してきました。
SpinMediaはVibeの紙媒体とオンライン「Vibe.com」の権利を獲得しました。
メディア企業SpinMediaが運営する音楽メディアには、オンラインサイト「SPIN」や「Stereogum」、音楽コミュニティサイトの「Buzznet」や「Idolator」、そして音楽ブログ・アグリゲーションサイトの「Hype Machine」があります。
2013.5.02
≫続・音楽メディアを巡るあれこれ〜食べログ研究と「影響力はどこから生まれるか?」という話 | 日々の音色とことば
2013.5.11
≫「音楽メディア」を巡るあれこれ(3) 〜「NAVERまとめ」と、瓦解するプロとアマの境界線 | 日々の音色とことば
2013.5.31
≫日本からはクラブカルチャーはなくなります。 | Strings of Netlife @ tumblr
2013.6.04
≫やっぱりわたしはCDを音楽聞くために買ってなかった | インターネットもぐもぐ
2013.7.07
≫シンプルで分かりやすい!過去30年間分の音楽メディアのシェアをペイント風に可視化したインフォグラフィック | All Digital Music
2013.7.11
≫宇川直宏「FREEDOMMUNE 0<ZERO>2013 」インタビュー | ナタリー
≫広告とコンテンツを一体化する方法 | AdverTimes
2013.7.31
音楽ニュース&レビューの総合サイト『Real Sound(リアルサウンド)』オープン
2013.7.31
≫だれがメディアの価値を追いつめているのか | ハフィントン・ポスト
2013.8.05
≫音楽ビジネスで「リアル体験」も変え始めたデジタル化の威力 | 日経ビジネス
2013.8.07
≫老舗新聞ワシントン・ポストの身売りで米メディアは大騒ぎ | GQ
2013.8.10
≫紙の本を出版する4つのメリット | BLOGOS
2013.8.12
≫音楽作品を、「教育」に配慮して批評するメディアが必要―原雅明 | RandoM
≫紙媒体出身ライターとウェブメディア出身ライターの違い | ASSIOMA
2013.8.13
≫第74回:紙の編集という呪縛 ~紙のウェブ化ではない新しいかたちとは?~ | コラムスピン
これまでのように大量に作って、大量に置いてもらい、大量に売る、というメガなメディアは、無くなって行くのかもしれません。しかし、細やかな領域をカバーし、よりニッチな嗜好を充たすことのできるメディアや売り方が求められてきているようです。
きっと、本当に“売れる”電子書籍やウェブコンテンツが登場するのは、紙媒体を軸にしてきた編集者たちが本格的にそれ以外のことへ取りかかり始める、これからなのではないかと思っています。
2013.8.18
≫音楽ストリーミング「Deezer」が英国音楽メディア「Clash Music」とパートナー契約を締結 | All Digital Music
2013.8.19
≫Web編集に求められるアプローチ | Parsleyの「添え物は添え物らしく」
だらだら記してしまったけれど。例えば写真のグラビアやイラストなどグラフィカルに見せたい際には現状は紙の方が向いているし、単発のレビューならば動画やECサイトへのリンクを絡めることができるWebの方は手軽ということになったりもするので、コンテンツごとに最適なツールを使っていく、ということが今後ますます求められていくことになるのだろう。
もっというと、紙とWebを組み合わせて一つのブランドとして「メディア」を作っていくというのが理想なのでは。相当難しそうだけれど、Parsley個人としてもチャレンジしてみたいと思っています
2013.8.21
≫月刊音楽誌「CROSSBEAT」次号をもって休刊 | ナタリー
シンコーミュージック・エンタテイメントの月刊音楽誌「CROSSBEAT」が、9月18日に発売される2013年11月号をもって休刊することが明らかになった。
「CROSSBEAT」は1988年に創刊され、先日創刊25周年を迎えた。定期刊行誌としては一旦休刊するが、今後は不定期でムックや書籍刊行を行い、情報発信についてはWEBに移行する予定とのこと。また夏フェス特集や年末の年間ベストセレクション特集など、「CROSSBEAT」恒例の企画は今後もムックの形で継続していく。
≫クロスビート月刊誌休刊に寄せて | THE MAINSTREAM
2013.8.22
≫世界の音楽の今」を語る行為って、そんなに値打ちのないことなのか? | THE MAINSTREAM
2013.8.23
≫安藤美冬『冒険に出よう』7万部突破の謎 部数の耐えられない軽さ – 常見 陽平 | BLOGOS
2013.8.24
新譜中心、複数人によるディスク・ガイド・ブログ「正直リスナー」がオープン。

2013.8.25
≫ぼくとおんがくざっしのおもいで、そしてこれから+電子書籍の宣伝 | レジーのブログ
レジー「まあ「音楽を伝えることを商売にする」のは大変な時代になってるのは間違いないけど、やりようによってはまだまだ開拓できる領域のある分野だと思います。そういう意味では刺激的な時代ではないでしょうか。ただやっぱり思うのは、ウェブ上のディープな音楽言論空間っていわゆるJ-POPとかロキノン系とかそういう音楽が俎上に乗りづらいんだよね」
司会者「日本の音楽を扱う場合でもインディー寄りのものが多いですね」
レジー「J-POPとかロキノン系とか「ある層から見ればバカにされがち」な音楽、この区分けの話は以前も一度取り上げましたけど、そういうのが本気で好きで、発信意欲があって、かつ書く力もある人ってのがあんまりいないのかなあ。この辺の領域ってこれまでは何となく商業媒体の牙城だった気がするんだけど、その構造が崩れつつあるってことだとも思うので、僕としてはそこのスペースを埋めていければと思っています。長くなってきたので今回はそんな感じで」
≫そして、メタルと老人が残った ーー洋楽誌『クロスビート』休刊に寄せて | Real Sound
しかし、「洋楽誌の終焉=音楽雑誌の終焉」と短絡的に考えるべきではないと、最後に言っておきたい(音楽雑誌全体の未来については本稿の本題ではないので機会を改めたい)。音楽を洋楽と邦楽に分けること。そしてさらに洋楽の中でも、現在でも比較的リスナーが残っているティーンアイドルやR&B/ヒップホップやクラブミュージックを周到に排除して、白人のロックを中心に据えること。『ロッキング・オン』や、ある時期からの『クロスビート』が拠って立ったその場所は、ある世代のある層に限定された、日本国内だけの極めてイビツな風土であった(それに比べれば、音楽をジャンルで限定したメタル誌のような存在はまだ健全だし、海外にも類誌は多く存在してきた)。そして、そのイビツな風土から生まれ、80〜90年代にその全盛期を迎えた洋楽誌の終焉は、ネットの影響とかを語る以前に、日本人のアングロサクソン系白人ロックに対する幻想の終焉が導いたものと言った方が、より正確だと自分は考えている。
2013.8.29
≫ナタリーがニッチ分野で成長し続ける理由、唐木元さんに全部聞きました。 | 東京編集キュレーターズ
田端 さっき楽屋でナタリーのここ7年間のPVの推移グラフを見せてもらったんだけど、すごいね、ある意味。
唐木 ある意味(笑)。というのは1次曲線、完全に直線ってことです。ただダラーっと微増が、一定の割合で続いてる。へこみもないけど、急増もない。だからブレイク感なんてない。ずっとジワーっとやってきたんです。なぜか。理由はニッチなジャンルだからですよ。LINEやfacebookみたいなコミュニケーション、メディアで言えば芸能とスポーツ、付け加えるならギャンブルとお色気。これは国民的なパイがあるから、2次曲線を描くような成長ができるジャンルなんです。notニッチなの。田端 音楽はニッチじゃないんじゃない?
唐木 いやー、みんな中学校の教室を思い浮かべてほしいんだけど、たしかに光GENJIやおニャン子の話はみんなしてたよ、芸能だから。でもギター持ってきて練習してたのはたぶん1人か2人でしょ。休み時間にマンガ読んでる子だって教室に1人か2人。昼休みに小説読んで過ごしてた子も1人か2人だよ。そういう教室に1人か2人しかいないジャンルっていうのはニッチだし、僕らはその子に語りかけるメディアだから。ゆえにニッチなジャンルは放物線を描けない。だから大きな資本が手を出さないんです。商売になりづらいから。
2013.8.31
≫メディアとプラットフォーム――情報の責任の行方 | GQ
2013.09.02
≫未来の Web メディア/その実装形とは | 藤村厚夫 Media Disruption
2013.9.04
≫「レーベルはダメだ」、バイラル動画で有名なOK Goがカンヌライオンズで語った音楽マーケティングとブランドとの共創とは?(インタビュー全訳) | All Digital Music
2013.9.09
≫存在感増す「まとめサイト」、その影響力・信頼性に注目 — 電通 PR「情報流通構造調査」 | japan.internet.com
2013.9.16
≫それはパートナー? それとも競合者か/Flipboard の新展開 | 藤村厚夫 Media Disruption
2013.9.24
≫ネットメディアの「呼吸」に慣れるということ | Parsleyの「添え物は添え物らしく」
2013.10.10
田中宗一郎による今、最高にキテるポップ・ミュージックを発見するには最適の音楽サイト「the sign magazine」がオープン。

2013.10.17
≫職業人としての編集者は生き残ることができるのか「提供価値」は何かという基本に立ち返って考える | 日経ビジネス
2013.10.18
≫文化のシフト、音楽メディアの変化 ──『タイニー・ミックス・テープス』、インタヴュー | ele-king
■あらためて音楽メディアの役割をどのように考えているのか教えてください。
M:それはとても重要だと思う。僕のキャリアがそれに依存しているというだけでなく、書くこと、考えること、音楽について話すことは音楽そのものと同じぐらい重要だと思う。もちろん、どうしようもない文章もあるけど、この文化的シフトを心から歓迎する。
2013.10.23
≫「ジャーナリズムは生きる道がない」という閉塞感の打破を目指すIT起業家たち | 瀧口範子「シリコンバレー通信」
2013.10.24
≫新聞サイトに集客させるには、新聞ブランドよりも記者ブランドで | media pub
≫「WHAT’s IN?」休刊撤回を発表、定期刊行継続へ | ナタリー
2013.10.25
≫堀江貴文さん「これからは個人が強力なメディアとなる。」| Gizmode
2013.10.26
≫読まれる記事にするための、タイトルのつけ方2013年度版 | 焼きそば生活
2013.10.30
≫新興メディア「リアルサウンド」が公開3か月で1000万PV達成、音楽メディアNo.1へ向け邁進 | TechWave
2013.11.01
≫ブログとソーシャルの補完関係が、いよいよネットの主役になってきた | わかったブログ
JAMBORiii STATION x Musicman-NET「音楽どうする会議」 音楽ライターはどうする? 〜 日本版Pitchforkってあり?〜が渋谷ヒカリエで開催される。

2013.11.03
≫デジタル雑誌なんていらない? | 本とeBookの公園
2013.11.10
≫ニュースメディアの文法が変わる/新興メディアの主張 | 藤村厚夫 Media Disruption
2013.11.11
≫【レポート】音楽どうする会議 第一回 テーマ「音楽ライターはどうする?」 | Musicman-NET
最後に”今後の音楽ライター像について”振られた石井氏は「音楽ライターだけで生計を立てるのは非常に厳しい」と現状を語りつつ、「批評やインタビューの需要はなくなっていない。とにかく場所がある限りは発信し続けることが大事」と会場の音楽ライター志望者に語りかけた。また「書き手の意志・主義・主観を大事にしてくれるサイトが増えたら嬉しい」と今後に期待を寄せた。
「音楽ライターになりたいと思っている若い方々がこれだけいらっしゃるということ自体、ネット上にニーズが生じている証拠なので、Real Soundを何とか形にしていきたい」と神谷氏。
小林氏は「メディアを独自に作られてやっている方も多いと思いますが、どこか大きなプラットフォームに乗っかるのも手だと思いますし、そういったプラットフォームが今後増えていけば、音楽に関して何かを述べていくことでお金にするということは十分可能だと思います。今もアーティストの皆さんは素晴らしい作品を作っていますし、すごく真剣な思いで作品を作っています。その熱量を直接的に伝えるためには、愛をもってそこに携わっていく、批評していくことが必要になってくるんじゃないかと思います。音楽は本来楽しいものなんですから、悲観することなく楽しんでやっていきましょう!」と客席に語りかけ、トークセッションは終了した。
2013.11.12
≫「音楽どうする会議」に岸田繁が反応 | togetter
こんなもんでしょうか。
FOLLOW