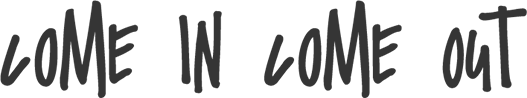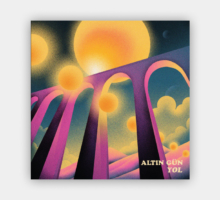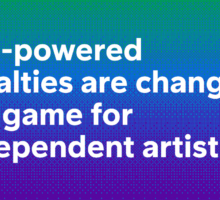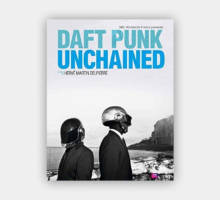ソーシャルメディアの普及で人の関心が個人にフォーカスされるようになってきたとか、スマートフォンの普及とそれに伴うサービス提供の変化によって音楽の出会い方聴き方が変わってきているとか、娯楽が増えてきて音楽が日常を占めるウェイトが相対的に少なくなっているという話がよくある。
レコード協会の2012年度音楽メディアユーザー実態調査によるとそもそも無関心の人、以前から知っていた曲しか聞かない人も増えている、お金も使われなくなっている。いち音楽ファンとしてそれは寂しいことだと思う。
一時期、音楽ファンにとって音楽を発見する場、アーティストにとってファンとコミュニケーションをとる場所として機能していたMyspaceの役割はYouTube、SoundCloud、Bandcamp、Twitter、Facebook、Instagramに移っていった。今年大胆なリニューアルするもイマイチ感は拭えない。
一方でMyspaceに代わる役割を担っているYouTubeの登場以降、さらにここ最近のSoundCloud、Bandcamp登場以降の音楽シーンは非常に面白く音楽そのものが衰退するということは絶対にない。コンピュータのパフォーマンスが向上し、音楽を作るための魅力的なソフトウェアもたくさんリリースされ、音楽制作そのものも用意にできる。そしてウェブサービスにアップすることで聴いてもらえる。
また、音楽を語る行為も同じくらい面白くなっている。その中でも最高なのは音楽ブログでありネットレーベル。YouTube、SoundCloud、Bandcampの音源が貼ってあり、すぐに体験できる。そして聴きながらテキストを読んで、その音楽への関与を深める、人で音楽を追っていく。今もっともディスカバリー性と継続性のあるメディアだと思う。
音楽も音楽批評も今一番おもしろい。まぁ世の中だいたい今が一番面白いんだけど。肌感覚だが、そのシーンを楽しんでいる人を数で表すとしたら数万人くらいなのだと思う。僕らにとってのメインストリームが、今音楽を掘っていない人、関心のない人にとってもメインストリームになったら世の中はめちゃくちゃ面白くなると確信している。
もっと音楽を日常的に語れる状況を作りたい。意識を向けさせたい。音楽が好きじゃない人にも好きなってもらうきっかけを与えたい。自分はここをライフワークにしていきたい。そもそもなんでこんなことを考えるかというと、うちの家族はそれぞれ写真をやっていたり、日本画を描いていたり、版画をやっていたり、コンピュータでイラスト描いているような人だらけだったというのが一番大きい。そういった状況を外から見てみると世間とのギャップにビビったというか。個展を開いたり、人の個展に行ったり、ギャラリーに遊びに行ったり、美術館に行ったり、外で絵を描いたりすることはよくある行為ではなかったらしい。
それらが仕事だった時期もあるし、趣味であった時期もある。母親はすっと絵が描きたいみたいで、こっちからすればそれがお金になるなら、それ以上のことはないんじゃないかなと思っていた。でも個展を開いても知り合いにポストカードを送ったり近所に人にお話したりするくらいで、結局来てくれるのは身内だけだ。それはそれで楽しいんだけど、もっと多くの人に見てもらうには、もっと多くの人の日常にアートが入っていくにはどうしたら良いんだろうとずっと考えていた。
絵画やグラフィック、制作で言うと今はBase、Stores.jp、FANCY、Pinterest、Instagram、Esty、Artsyといったウェブサービスがある。やっぱり今が最高に楽しい状況だ。こういったポジティブな状態にあるが、それはやっぱり今まで好きだった人が可視化されただけで、実態は小さなムラに変わりないんじゃないとネガティブに思ったりもする。
でもそれらのムラの熱量は高く、ムラ同士のクロスオーバー、コンテクストの合体も起こってきていてポジティブに捉えている部分のほうが大きい。
で、やっぱりビジネスの話もしないといけない。経済と文化の両輪をバランスよく回すことができれば素晴らしいと思っている。お金が落ちるというのは大事なこと。感情論だけど音楽で飯を食べる、写真で飯を食べる、版画で飯を食べるというのは素敵なことだと思う。それって社会も心も豊かな証拠なんじゃないだろうか。もちろんOTONARIにあったように、アーティストにも様々なスタイルがあることは分かっていて、何よりも作り手が尊重されるべきだと思っている。
今の日本の状況というのは、特に音楽において、経済の車輪がどんどん大きくなっていって勝手に爆発して吹っ飛んでいったようなものだと思う。「稼ぐ」という言葉への悪印象を植え付けただけだった。今は吹っ飛んでいった先でSpotifyというバズワードに振り回されているようだ。
経済と文化の両輪のバランスをとりながら回していくには具体的にはどうしたらよいんだろう。
それを音楽メディアという観点から語りたいね、というのが登壇させていただいたTOKYO BOOT UP!Conference Dayだったわけですが、1時間でしっかり収めることは難しく、ややグダってしまった感も否めない。申し訳ないと思いつつ、ニュアンスだけでも伝わり、明日のアクションにつながれば幸いです。ご来場していただいた皆様どうもありがとうございました。
以下に一緒に登壇してくれば炎上マイスターAiさんのツイートを埋め込み、補足をしながら振り返ってみたい。
僕が言いたかった話は最後に集約されています。音楽が経済としてもカルチャーとしても盛り上がるために、(大山くんの言葉を借りれば)もっともっと日常的に音楽について発信して行こう、ということ。発信の絶対量が増えれば、潜在的な音楽ホリック要素を持っている人の目に届く可能性が高まるから。
— Ai (@Ai_Tkgk) November 16, 2013
上でも述べたがこれが結論である。何よりもまず音楽体験が日常になっている音楽好きが盛り上がり、どんな形でも発信をして、楽しむことが大前提であり、最も大切である。
で、発信の仕方はなんでも言い訳です。今やブログやSNSなど個人レベルでやれることはいっぱいある。内容だって、自分の好きなことばっかり書いてたっていい。そこに共感者が集まっていって、同じ趣味や価値観を持つムラが出来上がる。
— Ai (@Ai_Tkgk) November 16, 2013
そのムラの中で好きな音楽に対する圧倒的な熱量を高めて行けば、強いムラが沢山出来てくる。そして、ムラの中で強い発信力を持って行けば、どこかでいわゆる力のある音楽メディアから声がかかり、憧れの場所で書くことができる、ということも実現できるかもしれない。
— Ai (@Ai_Tkgk) November 16, 2013
そんななかでレジーのブログでお馴染みのレジーさんは素晴らしい一例を作ってくれた。
(´-`).。oO(そう言った意味で、僕にとってレジーさんはそのモデルケースを作られた方で、本当にすごいと思う。そして頑張れば、音楽業界に身を置かなくても仕事が出来るということを証明してくれた点で非常に有難い存在です)
— Ai (@Ai_Tkgk) November 16, 2013
で、それぞれ凝集性を高めながら巨大化していくムラ同士がクロスオーバーしていくことで、ムラ同士の交流から新しいカルチャーやムーブメントが生まれてくる。そうして、また規模が広がっていって(経済的な意味も含めて)力が強まって行く。
— Ai (@Ai_Tkgk) November 16, 2013
で、そのクロスオーバーの手法もなんでもいいわけです。リアルの場という意味で例えばフェスでもいいし、REAL SOUND様々なジャンルを取り上げて行くメディアでもいい。
— Ai (@Ai_Tkgk) November 16, 2013
ここが一番難しい部分だ。アプローチの一つとして、様々なクラスタが集まるフェスティバルは有効な場所だ。オンラインではHype MachineやShuffler.fm、各種ストリーミングサービスもそうだ。また特に個人にフォーカスし、音楽から新しいメディアに出会い、メディアから新しい音楽に出会うという点ではSpincoasterや正直リスナー、Hi-Hi-Whoopeといった複数人によるブログメディアやネットレーベルもそうかもしれない。勝手な解釈だが、そのくらいの期待をしてしまっている。もちろんそれぞれ面白くて更新をチェックしたくなる。
そしてそれらの熱量をマス向けにカスタマイズし、適した媒体で発信するの力をもっているのが商業メディアだ。
ただ、そのクロスオーバーの担い手は、できればすでにある程度の権威を持っている職業音楽業界の人達にしてもらいたい。そうすることでクロスオーバーの効果の波及ラインの半径が限りなく大きくなるから。
— Ai (@Ai_Tkgk) November 16, 2013
これは何も「音楽メディア」に限らないし、むしろ「音楽メディア」ではないほうが有効だと思っている。それはテレビかもしれないし、大手新聞かもしれないし、ファッション誌かもしれないし、ヤフトピかもしれないし、そのへんの街角や飲食店かもしれない。
その点で他のクラスタにリーチできるメディアに記事を提供しているReal Soundには大変期待をしている。
ムラ化→ムラ同士のクロスオーバー→化学変化からムラ同士の統合や共闘→クロスオーバー、のサイクルを繰り返すことで音楽に対する力が凝集されて行き、結果としてビジネスチャンスも様々な観点で生まれるのではないかと。
— Ai (@Ai_Tkgk) November 16, 2013
で、翻って個人の僕らはまずはムラ作りをしましょうよ。一人一人が発信して、住民を増やして行きましょうよ、と。そして、ムラを作るだけでなく、様々なムラに戸籍を置きにいきましょうよ、という話です。
— Ai (@Ai_Tkgk) November 16, 2013
とにかく今を楽しんでいる人に、今のようにその楽しみを発信していって欲しい。そもそも潜在的に音楽を求めている人はだいぶいると思うので、せめてそういった人たちに届けば最高だ(以下のインターFMの主張のように)。勝手な要望のような結論になってしまうが、今我々が言えるのはこれくらいだ。
前述のキャンペーンで多くの支持を集めたインターFMは、2013年よりステーションコピーを「The Real Music Station」に変更。「本物の音楽」を発信し続ける決意を改めて表明し、今日も放送を続けている。ピーター・バラカン氏は執行役員就任にあたり以下のように語っている。「元々音楽が大好きなコアなリスナー層だけでなく、潜在的に良い音楽を求めている人達は沢山いるんです。インターFMがリスナーのために良い音楽をかけていれば、もっと多くのリスナーがラジオを聴いてくれるようになるのではないかと考えています。それを実現するのは本当に大変な事だと思いますが、今、私たちがやらなければいけない」。インターFMの挑戦、それは失われつつあった「ラジオで音楽を愉しむ喜び」の再発見だ。最近新しい音楽との出会いがない、そう感じている方はインターFMを聴いてみてはいかがだろうか。
出展:FMラジオにもっと音楽をーー楽曲重視の編成改革を進める「インターFM」の挑戦
あくまでも音楽メディアや音楽サービスだけにフォーカスするとこういった話になっていくのだが、ここで具体的に触れていないのがアーティストがどうやって食っていくかという部分だ。そもそもこれはアーティストありきの話であり、アーティストが何か解決したい問題をもっていなければこれらの議論は成立しない。
仮に大多数のアーティストが表現で飯を食っていきたいと考えているならば、彼らにお金が落ちない商業音楽メディアや音楽サービスの存在は本当に素晴らしいのだろうか。それこそSpotifyに対するトム・ヨークの主張のように。
ここの問題点は「鶏が先が卵が先か」という話になることだ。極端に表現してしまうと、アーティストが存在しなければ文化が成立しないという一方で、まず届けなければお金につながらないということである。トム・ヨークが言うなら意味があるかもしれない、でも例えば僕が曲を作ってもどこかにアップしないと聴いてもらえないだろうし、アップしたって聴いてもらえるかどうか分からない。でも聴いてもらえないと好きになってくれない。だったらせめて人のいるメディアで配信しようと思ってしまう。(もちろんストリートライブという手段もある)
結局は何のために何をするか、それをする場はどこが適切なのかという話だと思っている。選択と集中、役割、それらのサイクルとバランス。全てがつながっている。何かにフォーカスして話をしていても、実は大きな前提や同じ理想があることを伝えないとそもそも伝わらない。
例えばビジネスの話は叩かれやすい。その原因のひとつに大前提を共有していないことがある。結局音楽の話をしてないじゃんと思われがちで、実際自分もそのように思うことがある。逆に音楽の話だけをするとその時は楽しいんだけど、あれっ結局どうすれば良いんだろうとなる。まず、何のためになぜ今その話をしているのか明確にしないと先に進まない。
最初は貝だったらしいじゃん、お金。山の民「イノシシとれたけど、魚と交換しない?」海の民「今日とれなかったわ〜貝渡しとくから今度これと交換で」とかやってたわけだ。お金そのものは富じゃない、富と交換する手っ取り早い手段でしかない。音源と野菜を交換でも良いけど、ちょっと持って帰るの面倒だし。お金の先にあるものが見えなくなってきたり、そもそもなぜお金を稼ぐ必要があるのか見えなくなってくると話が破綻する。これって超難しい。
イノシシがいるっていうことと、イノシシが超美味しいっていうこととを知ってほしいし、イノシシが美味いって皆で盛り上がりたいみたいな気持ちですよ。でもまずいイノシシもいるわけですよ。ちょっと何言っているかわからないけど、そういう感じです。ただ音楽を食べて生きることできないからなぁ。
結局アーティストのスタンス次第ですよね。
タナソーの話と似たようなものだと思う。知らんけど。
これは個人と個人だけではなく、あらゆる関係性について言えること。何かしらの理想をシェアしていさえすれば、互いに依存するのではなく、互いを鼓舞し合いながら、先を目指すことが出来る。音楽に恋するのも同じこと。批評は、その対象と同じ理想を共に目指す。読者と同じ理想を目指す。>RT
— 田中宗一郎 soichirotanaka (@soichiro_tanaka) November 14, 2013
何故、褒めてばかりで、何も言わない情報だけの批評、あるいは、状況についてばかり語る批評が幅をきかすかと言えば、そこに理想がないから。何故、慰めばかりの音楽、聴き手を無条件に肯定してばかりの音楽が幅をきかすかと言えば、やっぱり理想や夢がないから。だからこそ、生まれるのは依存ばかり。
— 田中宗一郎 soichirotanaka (@soichiro_tanaka) November 14, 2013
忌野清志郎の「愛しあってるかーい?」ってのは、要するに、そういうこと。最初は引用だったとしてもね。「もしかして、誰も愛しあってないんじゃねーの?」ってこと。NO MUSIC NO LIFEなんてのは、ただの依存。音楽は、そんなものなくても生きていける!と強く言える人のためにある。
— 田中宗一郎 soichirotanaka (@soichiro_tanaka) November 14, 2013
時として、音楽とリスナーは出口のない依存関係に陥ってしまいがち。良くも悪くも音楽には力があるから。だからこそ必要悪としての批評も存在する。心地よい依存関係に冷や水を浴びせ、愛しあうという茨の道をもう一度用意する。決して楽しい作業じゃない。でも、そうしないと、また理想が遠のくから。
— 田中宗一郎 soichirotanaka (@soichiro_tanaka) November 14, 2013
この話、まだまだ続けていきたい。
企画 というよりは、ある程度固定でひとが集まったりして、そこには音楽も大きな軸としてあって、って場所を作るのが目標なんです。夢というか。そのひとつの形がゲストハウスだったりする。そんな話も昨日のTOKYO BOOT UPでできたらよかったかなあ なんて今さら思ったり。
— emr_81 スズキエミリ (@emr_81) November 17, 2013
何にせよ。今、またここから、ですね。
— emr_81 スズキエミリ (@emr_81) November 17, 2013
続く!
FOLLOW