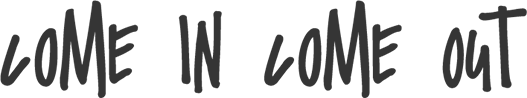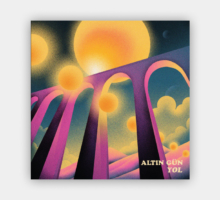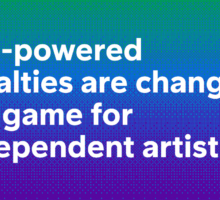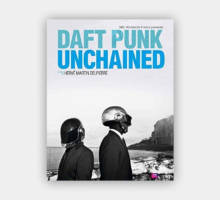面白い記事やエントリーがあったので紹介していきます。
映画はもはや大衆娯楽ではない
いずれにせよ、スタジオシステム全盛期の「映画は大衆娯楽」という先入観とは決別する必要がある。
観客はもはや「大衆」としては存在していないし(それは情報が国境を越えて迅速に伝達されることとも関係があるが)、映画に対する嗜好は非常に多様なものになっている。その需要に対して採るべき戦略は、食品や自動車の生産におけるそれとはわけが違う。
観客はある作品のあらすじや映像スタイルや設定に魅力を感じるから、見ようという気になる。そして常に何か新しいものをそこに求める。更には、俳優の演技や映像の品質や演出さえも評価される。それが現代の映画を取り巻く現実である。
なるほど、確かに。音楽もそうだけど「大衆娯楽」だった時代と比べると趣味娯楽はより細分化しているし、そのジャンルも細分化している。一方で人間は大衆であり続ける部分もある。浮動の部分だ。興味がありトライブに属している部分では「大衆」ではないかもしれないが、あまり興味がない部分では流行に流されたりもする。今はとにかくたくさんのトライブが存在している、こと音楽や映画といったカルチャーでは分化しがちであるように思う。これにはあとあとブログで書いていきたいテーマです。
人気のソーシャルメディアはどう儲けている?
人気ソーシャルメディアがどう儲けているのかを一枚のインフォグラフィックで
Twitter、Foursquare、Yelp、Tumblr、Vimeo、LinkedInなどの30のソーシャルメディアのビジネスモデルをわかりやすいインフォグラフィックで表現。広告、ウェブアプリ、有料会員、モバイルアプリ、アフィリエイトに分類している。勢いの止まらないPinterestはアフィリエイト。Pinされたイメージがあったウェブサイトへのアクセス、そこからの消費で稼いでいる。まだ安定したビジネスモデルが確立していないが、まずはサービスを作って細かいことはあとからという方針らしい。
音楽違法DLに刑事罰
音楽違法DLに刑事罰 6月法案化へ
今日のメインはこれ。
今時違法ダウンロードしている人いるのか?と思って周り見てみたら普通にいました。そりゃあ無料で手に入るならそれに越したことはないけども。でもラジオをテープに録音して…ってのと訳が違うと思っていて。片っ端からアルバムごとって…いや、それダサいよね?アーティストだってタダで聞かれるはプロモーションとして割り切ったとしても、それでもしライブにも来ないとなると嬉しくもなんともないでしょう。
値段つけて売るっていうことがどういうことなのか、違法ダウンロードするやつは全く分かっていない。そしてこれを説明したところで伝わらないと思う。なぜ値段をつけて販売するのか、その意味を考えてみて欲しい。
っていう話は個人的な見解なのでどうでも良いとして、果たして法案化して本当に産業にプラスになるのだろうか。「インターネットがでてきた→やばい→インターネット取り締まれ」ではなく「インターネットがでてきた→やばい→ビジネスを変えよう」になるべきではないのか。そりゃもちろん違法ダウンロードの取り締まりも必要だが、取り締まったからと言って音楽ソフトが売れるのだろうか。
インターネットのあり方と同時に新しいビジネスモデルも考えなければならない。違法ダウンロード、アップロードする奴も問題ありなんだけど、業界にも問題大有り。アーティストにだってもっと柔軟性が必要だ。じゃあどうしていけばいいのだろう。音楽×ソーシャルメディア、これはやり方次第で今よりももっと活用できると思っている。この話は続きます。
FOLLOW