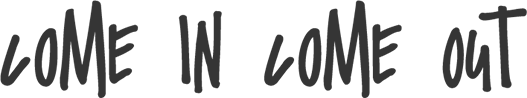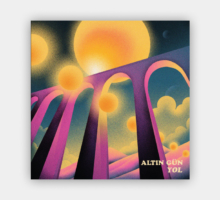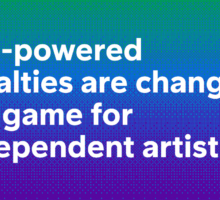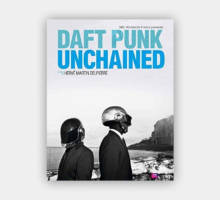今週末、フジロックフェスティバルが開催される。The Stone RosesからThe Specials、Radiohead、Beady Eye、Noel Gallagher’s High Flying Birds、Ray Davisというビッグネームはもちろんのこと、今年新作をリリースしたSpiritualized、Cloud Nothing、The Heartbreaksもきっと良いライブを見せてくれるだろう。
僕は3日間参加するので、会場で見かけたら是非気軽にお声かけしていただきたい。
さて、フジロックフェスティバルはその名の通り、音楽の祭典である。
以前このブログのエントリー「ライブイベントのハレとケ」でも書いたように、フジロックは自然の中で音楽を楽しめる完全な非日常「ハレ」の空間である。天気が変わりやすい山の中で、音楽を楽しむ、キャンプをするというマゾ要素がその「ハレ」度を増幅させる。そのマゾ要素が中毒となり、音楽ファンだけでなく、フジロックフェスティバルそのものにロイヤルカスタマーがついているのである。
このようにフェスティバルにおいては日常「ケ」を介入させず、非日常の空間をいかに作り上げるかが、ファンを楽しませる上で重要となる。
フジロックを共有するために
さて、ではフジロックフェスティバルに参加できなかった音楽ファンやフジロックファンはどうしたら良いのだろう。フジロックや音楽に対する気持ちを現地と共有することはできないのだろうか。
まず考えられるのはTwitterやFacebookといったSNSだ。これらのSNSにはフジロックの公式アカウントが作られている。
見てみると、TwitterとFacebookでは投稿には大きな違いは見られないが、フェスティバルが始めるとリアルタイム性の高いTwitterはフェス体験の共有する上で大きな力を発揮するだろう。
では、どのようなコンテンツを発信すれば良いのだろうか。以前も「ロックフェスティバルのTwitter利用を考える」で書いたが、メインになるのは「天候」「物販」「飲食」「ライブ情報」の4つだ。
天気の変わりやすいフジロックでは「天候」について発信するのは必須だろう。「物販」では、待ち時間や在庫をコマ目にツイートするのが良いだろう。「飲食」も「物販」と同じ使い方で良いだろう。フェスごはんはフジロックフェスティバルの音楽ではない目玉の1つだ。どれが人気か、どのくらい待つのか。フェス期間、どの時間帯が一番お客さんが多いの少ないのか把握しておく必要がある。少ない時間帯に合わせてツイートしていくのはどうだろう。もちろん写真を忘れてはいけない。ファンの腹を空かせるのだ。
しかしこれらのコンテンツはどちらかと現地にいるファン向け。「飲食」は参加できなかったファンを刺激することもできるだろうが、これだけではフェス期間中にTwitterを見る必要はない。そこで「ライブ情報」だ。
「ライブ情報」はフェス参加者にとっても、不参加者にとっても有益なメインコンテンツだ。最高のライブを最高の言葉と写真で届けよう。
Twitterアカウントの運営者は是非バックステージにお邪魔してほしい。現地のファンも見れないバックステージでのアーティストの様子を伝える。アーティストにコメントを貰えれば最高だ。写真付きでツイートすべきだ、感動的に。その出演者のファンは最高にテンションが上がる。そして不参加者もライブを擬似体験することができる。ライブ中は写真と文章で、その熱狂を伝えよう。知っていればセットリストをツイートするのも良いだろう。ライブが終わったら、再びバックステージへ。アーティストにまたコメントを貰おう。
だが、これらを一人でこなすのは酷だろう。そこで、ファンや現地のスタッフにアカウントを公開してしまうのはどうだろう。1つのアカウントを複数人で管理するのだ。ベテランのフジロッカーから初参加者、物販、飲食、PA、生の声を代わりに届けてもらう。
といっても1つのアカウントでも無理があるかもしれないので、Twitterユーザーをピックアップし公式サポーターにしてしまう、公式サポーターのリスト作って公開するというのも良さそうだ。
フジロック公式アカウントは公式の強みを活かしつつ、ユーザーに協力してもらうことで、インタラクティブなフェスティバル空間が出来上がる。非日常を日常のなかで垣間見ることができるのだ。
公式ファンサイトもTwitter・Facebookを運営しているし、結構イケるんじゃないだろうか。ってかファンサイトの方が更新が活発だったりするし。当日速報サイトも既にオープンしている。
Facebookページは英語での情報発信も行なっているので、海外向けにシフトしてしまうとか「いいね!」を比較的もらいやすい情緒的な文章と魅力的な写真の組み合わせも良いだろう。Facebookでは共有方法が「いいね!」「コメント」「シェア」と3つあるので、Facebook上でフジロックの露出が上がるのではないだろうか。
写真
などといろいろ書いても、一番フェスティバル空間を共有できるのは参加者の投稿する写真や公式での動画配信だろう。しかし、フジロックではライブをファンが撮影することはできない。
会場内にカメラ・ビデオカメラ等持込みは可能ですが、出演アーティストの撮影は禁止です。又、録音機器の場内への持込みは一切禁止です。
もちろん、音楽を聴く行為がメインであって、写真を撮ることは決して重要ではない。しかし、それらの写真を含めた参加者のフジロックストーリーはプロモーションの1つになると考えられないだろうか。確かに高野氏が「音楽の体験共有を増幅させるために前提となる2つのこと」というエントリーで述べている通り、そこには「然るべきタイミング」があるはずだ。
でも個人的な感覚としては撮影禁止は納得できない。そりゃあもちろんバシャバシャやっている人間がいれば「なんだコイツ、何しにキテンダ」と思うだろう。実際に好きなバンドの海外ライブの映像を見てみるとファンは写真を撮りまくっている。最高に大好きな音楽を奏でるアーティストがそこにいるのだから気持ちは分かる。大いに分かる。しかし、一度携帯しまえやー!とは思う。とかいう私もカメラ小僧ではあるのですが。禁止しても遠慮がちに数枚撮ってしまうのがリアルな話。だったら撮った写真を使ったプロモーションを考えたい。
いや、嘘、わっかんなくなってきた。どっちが良いのだろう。どっちが良いって話でもないか。でも自分は撮りたいし、それを共有したいな。
とりあえずアーティストとかライブとかではなく、普通に写真撮りたいのでカメラ持っていきます。
ライブ映像
今年のフジロックはスカパー!で生中継される。しかしこれには疑問がある。
まず、「放送されるアーティストが未定であること」なぜだろう。普通に考えて、どのアーティストが放送されるのかは知っておきたのではないか。
次に「午後3時〜6時20分」の放送であること。ちょっと待て。一旦待ってくれ。考えなおさないか。なんだろうこの中途半端な感じは。
そしてそもそも「スカパー!で放送する」ことだ。スカパー!での生中継に限ることで、その情報にアクセスできる人間の数はかなり絞られる。そもそもスカパー!での生中継の目標がどこに設定されているのか分からないので、何とも言えないが、「フジロックに関心をもたせ、動員する」ことは恐らく目標の1つだろう。たぶん。フジロックに参加したことのないスカパー!利用者を取り込むこと。
そもそも参加できなかったフジロックファンはわざわざスカパー!には登録しない。絶対しない。このために契約した人はいないだろう。これをキッカケに契約する人はいるかもしれないが。いや、本当にいるのかな。放送されるアーティストもわからない上に、午後6時20分にか放送されない中継のために?まじで?
でも、これって効果あるのだろうか。フジロックに行ったことのない人で既にスカパー!の利用者には雰囲気は伝わるだろう。でもそこから先がない。スカパー!はスカパー!で完結しているのだ。そこからPCを立ちあげて、スマートフォンを立ちあげて、公式サイトを訪れて・・・。もし仮に、SNSでスカパー!でフジロックを見ていること、そして感動したり、行きたくなったことを共有しても、他のユーザーはそこ元となった情報にアクセスできないのだ。スカパー!利用者でもわざわざテレビを付けなければならない。スカパー!を利用していない場合はチューナーを設置して・・・手間がかかる。
これはスカパー!に限った話ではなく、Spotifyといったソーシャルミュージックサービスにも同様のことが言える。Twitter・FacebookでSpotifyで聴いていることをシェアしても、それを見たユーザーがSpotifyユーザーでなければ音楽を聴くことはできない。空振りシェア。しかしアプリやウェブサービスなら登録は簡単だ。
一言で言うと、スカパー!は、共感し、ライブに足を運び、感動を伝達するサイクルのどこにも入ることができない。極端に言うと、だ。だって導線がないから。
コーチェラ・フェスティバルに学ぶこと
サンプルとして非常に有用なのがコーチェラ・フェスティバルのソーシャルメディアを利用したブランディングだ。コーチェラ・フェスティバルは11ものソーシャルメディアを利用してファンとの繋がりを作った。
フェスティバルそれぞれに特性はあるし、この利用方法を踏襲するべきと言っているわけではない。しかし、このウェブ上の導線の設置は素晴らしい。YouTubeでライブ配信を見ながら他のSNSでコーチェラについてコミュニケーションを取るのが楽しい。
確かにフジロックフェスティバルは日常を垣間見せない「ハレ」の空間である。しかし、その閉鎖的な部分が参加へのハードルを高くしているように思う。上手く「ハレ」を見せて共有することで、そのブランドはさらに認知され、「音楽の日常化」に貢献できるのではないだろうか(音楽やライブはもっと日常的なもので良いはずだ)。
音楽ビジネスのゴールはどこか
これはフェスティバルに限ったことではないが、マーケティングや運営の「ゴールはどこ」なのだろう。
所謂、日本の音楽業界ってどこに向かって行きたいのだろうか。音楽ビジネスのゴールって一体何なんだろう。業界人はどう思っているのだろう。誰が儲けたいのか、誰を儲けさせたいのか。アーティストをどうしたいのか、ファンにどうなってほしいのか。
日本でもようやくストリーミングサービスが盛り上がろうかという今年、音楽ファンにとっては喜ばしいことのように思う。でも、何か行き当たりばったりな気がしないだろうか。
っていうかアレじゃん。アーティストはどう思っているのだろう。なんで音楽ビジネスの話をするとき、違法DLの話をするときに、コンテンツを作っているアーティストの意見がどんどん出てこないのだろうか。変にアーティストとリスナーに憑依した神のような意見を見かけることがあるが、結局それは当事者ではないのだ。
いや、まて、音楽の当事者って誰だろう。アーティスト、リスナー、レコード会社・・・。まずはアーティストだろう。コンテンツを作っている人間は何を思い、どう行動し、どんなゴールを見据えているのだろうか。
って感じで、最後に話ずれましたけど、フジロック楽しみです。皆さん、苗場でお会いしましょう。
FOLLOW